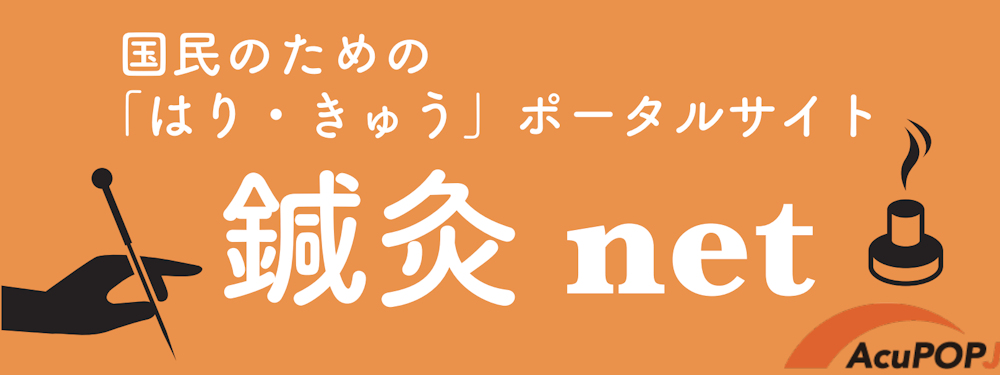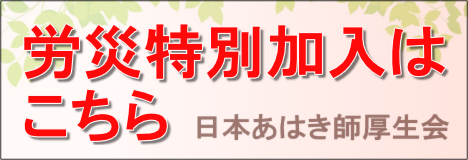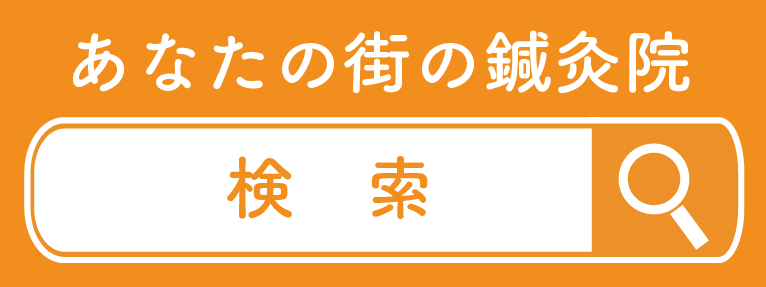報告令和7年度7月度学術講習会NEW
令和7年度7月度学術講習会

【日時】令和7年7月13日(日) 13:30~15:00
【演題】
・学術講習会①
「下肢障害で悩める人をゼロに近づける」
講師:日本足病学協会理事 Genki Style鍼灸整骨院 院長 岩井元気先生
【会場】大阪府鍼灸師会会館3階
外反母趾や変形性膝関節症(膝OA)は、テーピングや運動療法、装具など多角的なアプローチが可能な整形外科疾患である。今回の講演では、岩井元気先生が病態理解に基づく治療法の考え方について解説された。
(大阪府鍼灸師会研修委員 川口 直秀)

外反母趾は母趾が中足趾節(MTP)関節で小趾側に曲がり、外反母趾角(HV角)が20度以上の状態を指す。診断は足部背底X線でHV角とM1-M2角を測定し、変形度を分類する。類似疾患には強剛母趾、関節リウマチ、種子骨障害がある。発症要因は足部のオーバープロネーションで、アーチの潰れにより母趾への荷重が増し、変形が進行する。
治療は靴治療、運動療法、装具療法、薬物療法を経て、必要に応じ手術が選択される。
膝OAは50代日本人の3人に1人が罹患する疾患で、膝関節が横方向ストレスに弱い特性に不適切な歩行習慣が加わり、軟骨がすり減ることで発症する。治療方針として、股関節を正しく使った歩行や歩行速度を上げ横方向への負荷を減少させることが重要である。
歩行由来の疾患は歩き方を改善しなければ根治しない。外反母趾・膝OAでは靴療法が基本であり、縦のサイズ(レングス)と周径サイズ(ウィズ)の正確な計測が必要となる。
良い靴の条件はかかとがしっかりしていること、つま先だけが曲がること、靴がねじれないことの三点である。さらに適切なインソールの使用により圧力が分散し、症状改善が期待できる。
鍼灸治療では筋緊張を緩め、経絡を整える目的で経穴を選択する。
仰臥位では陽陵泉(三腓骨筋)、三陰交(長趾屈筋)、築賓(ヒラメ筋)、豊隆(前脛骨筋)、光明(腓骨筋)などを使用し、気が集まり散りやすい陽経の絡穴を用いる。
伏臥位では風市(腸脛靭帯、大腿二頭筋)、崑崙(短腓骨筋)、飛揚(腓腹筋)、臀部硬結などを用い、風市は臀部の力を引き出す目的がある。施術には寸3の1番鍼を2~3mm刺入し、5~10分置鍼する。
灸治療では跗陽、復溜(Kagerʼs fat pad)、解渓(距骨前脂肪帯)などを用い、脂肪帯の滑走性を高める。奇数壮で補法を行い 5~10 分施灸する。

根本治療には「カラダ(鍼灸・物理療法)」「モノ(シューズ・インソール)」「プラン(栄養、休養、運動計画)」の三要素が必要である。歩行で生じた症状は歩行から改善しなければならない。年齢や筋力の変化により従来の靴が合わなくなる場合もあるため、定期的な計測と歩行評価が不可欠である。
本講演を通じ、鍼灸師としては経絡治療を通じた筋緊張緩和と疼痛軽減を行いつつ、靴選びや歩行指導を含めた多面的な治療プランを提案することが求められると再確認した。
【日時】令和7年7月13日(日) 15:15~16:45
【演題】
・学術講習会②
「基礎から学べる鍼通電療法、電気温灸器概要」
講師:株式会社メディカルアート 代表取締役
つぼい鍼灸接骨院院長 坪井良寛 先生
【会場】大阪府鍼灸師会会館3階
古代にはシビレエイや電気ナマズを用いた治療が行われ、治療家は徒手療法や物理療法に加えて電気エネルギーを活用してきた。現代ではオームパルサー、ピコリナ、エスプリなど多様な鍼通電機器や電気温灸器が登場しているが、その性能を十分に理解し臨床で活かしている治療家は少ない。本セミナーでは、最新鍼通電機器の高度な機能と、設定次第で多様な効果を引き出せる可能性について詳しく学ぶことができた。
(大阪府鍼灸師会研修委員 川口 直秀)

鍼通電には禁忌が存在し、患者に不利益となる行為は避ける必要がある。
禁忌対象は、ペースメーカー装着者、知覚脱失のある者、循環障害者、重篤な動脈疾患のある者、妊婦、原因不明の発熱、強い皮膚疾患を有する者である。さらに、使用する鍼通電機器の添付文書を必ず確認し、メーカーの指示に従わなければならない。
周波数は 1 秒間に発生する電気刺激の波の回数で、単位はHzで表される。
鍼通電療法では波形が治療効果や刺激感に影響し、矩形波や棘上波が基本だが臨床では多様な波形が使用される。波形の違 いはプラス・マイナス電流の流れ方によって生じ、刺激の強さや体感が変わる。特にマイナス極は強い刺激として感じられるため、波形の性質を理解して使い分けることが求められる。
周波数は治療効果を左右する重要な要素である。内因性鎮痛機構には内因性オピオイド系とゲートコントロール理論がある。
低頻度刺激(2~5Hz)はエンケファリンとβエンドルフィンを放出し、効果発現には 20~30 分かかるが持続時間は長い。
高頻度刺激(50~100Hz)はダイノルフィンを放出し、30秒程度で効果が出るが終了後は効果が急速に消失する。ゲートコントロールは脊髄分節性鎮痛であり、痛み部位に刺激を与える必要がある。
パルス幅は 1 回の刺激が持続する時間で、短いパルス幅では鋭い刺激が感覚神経を優位に刺激し、長いパルス幅は深部まで 到達し運動神経や筋肉を刺激する。鍼通電では患者の体感と治療目的に応じて調整することが重要である。
臨床で使用するモードには、一定リズムのコンスタント、設定範囲内で周波数が変化するスウィープ、刺激を穏やかに変化させるモジュレーションがある。患者の感受性に合わせた選択が求められる。
定電流方式の機器は皮膚抵抗が変わっても一定の電流を維持するため、治療効果が安定する。電流は水の流れる量、電圧は水の勢いに例えられ、理解が容易である。
微弱電流療法は、創傷や急性外傷の修復を目的とし、50~100μA の微弱電流が ATP 生成を促進し組織修復を助けると報告されている。
温熱療法は表在温熱療法と深部温熱療法に分けられる。ホットパックや灸は表層のみを温め、深部組織には届かない。深部治療が必要な場合は超音波やラジオ波などの機器を用いる必要がある。
温熱療法では温度管理も重要で、43℃を超えると痛覚受容器が働き、治療効果が損なわれる。
電気温灸器は匂いがなく火傷のリスクも低いが、ヨモギの薬効を再現できない。また、機器ごとの禁忌事項が存在し、添付文書を確認の上で使用する必要がある。