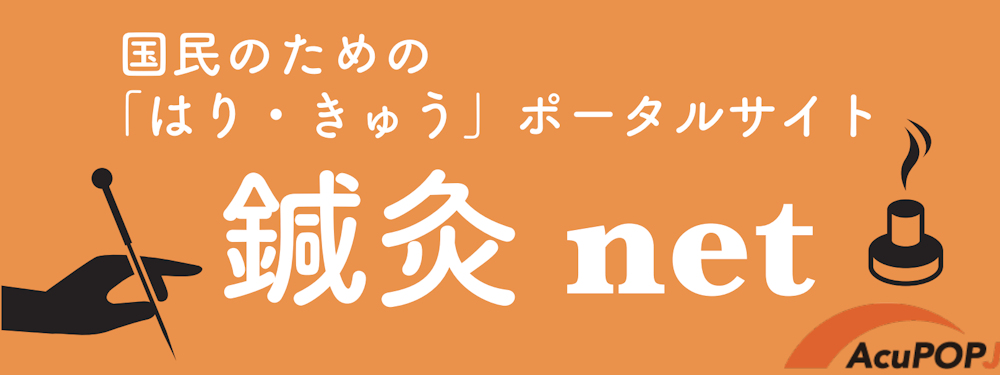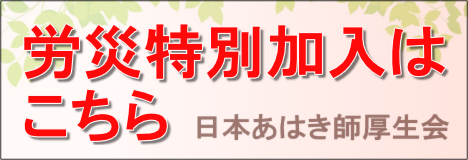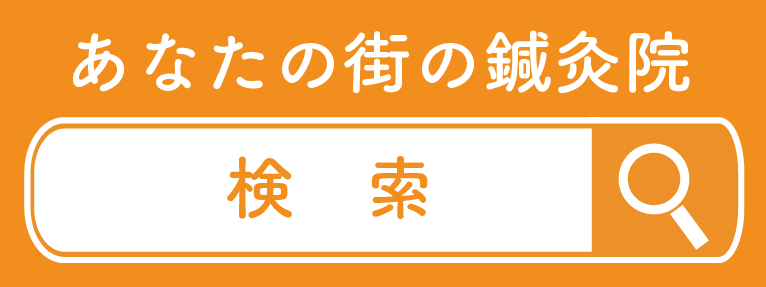霊枢勉強会報告
報告八月特別講義 『五蔵診察について』NEW
講師 :日本鍼灸研究会代表 篠原 孝市 先生日時 :令和七年(2025年) 8月10日(日) 第52回
会場 :大阪府鍼灸師会館 3階
出席者:会員(準会員含む)13名 会員外(日鍼会・全日学会員含む)22名 学生6名
*8月度は会場17名、ネット配信での受講が24名でした。
八月特別講義 『五蔵診察について』
○五蔵診察を考えるためのメモ (配布資料23ページ)
**( )内のふりがなは配布資料にはありませんが、読んでもらいたくて、入れてます。(松本)
○06 経絡治療と古典の五蔵病證(ごぞうびょうしょう)―――五蔵(ごぞう)は症状で診る、 その効果判定は、問診などの外からの観察による。 経絡治療の経絡は脈状(浮沈虚実)で診る、 その効果判定は、 脈状の変化を第一とする。 その接点は何か。
*接点は、今のままでは無い。
*たとえば、手の大陰(たいいん)の経脈が虚(きょ)した場合に、咳(せき)が出ることは少ない。 しかし五蔵病(ごぞうびょう)のしるしとしては、これはおそらく肺の実熱(じつねつ)であろう。 これは症状が重い。 そういうふうに見るしかないのではなかろうか。 接点を考える時は、関係するけれど関係しないという観点から観るしかないと思う。
○07 五蔵(ごぞう)の虚実寒熱(きょじつ・かんねつ)が、 六部定位(ろくぶじょうい)脈診の経脈の虚実と一致するならば、脈診は必要ない。 ただし、 五蔵病證(ごぞうびょうしょう)は症状が無いと、 病態を判定できない。
*今の五蔵病證(ごぞうびょうしょう)は症状がないと病態は判定できない。 五蔵の病證(びょうしょう)は脈状でわかるのではないかと言われているが、 それは副次的に脈診をしているだけに思う。 六部定位(ろくぶじょうい)脈診の虚実と一致しているということはないと思う。 それは別のものだと言える。
○08 経絡治療は、 症状が無くても、 脈状の浮沈虚実があれば病態(證)を決めることができる。 その病態(十二経の虚実)と蔵府病證(ぞうふびょうしょう)の関係は何か。
*手の大陰肺経(たいいんはいけい)の虚証では多くの場合、喘咳(ぜんがい)は出ない。 手の大陰肺経(たいいんはいけい)が虚して、 手の陽明大腸経(ようめいだいちょうけい)が実しているというふうに経脈(けいみゃく)がなった場合には、 肺の病證(びょうしょう)としての喘咳(ぜんがい)が出るということがある。 わたしは、そういう関係だと思っている。 肺と大腸の関係で、肺に来て大腸が実(じっ)するような関係、 本格的な実の状態になった時に肺(はい)の蔵(ぞう)の病證(びょうしょう)が起こる、 そういうものではないかと思う。
*肝の病證(びょうしょう)についても同様だと思う。 足の厥陰肝経(けついんかんけい)の虚証では普通、 肝の蔵象(ぞうしょう)は起こらない。 肝(かん)が実(じっ)する状態になった時に、肝の蔵象(ぞうしょう)というものがあらわれるというふうに、 今は考えている。
*蔵府(ぞうふ)のレベルと経脈(けいみゃく)のレベルというものは、そのような関係にあると思う。
○09 なぜ経絡治療は、 経脈を操作して、 蔵府(ぞうふ)を調整できるのか。
*経脈(けいみゃく)と蔵府(ぞうふ)がつながっていると考えているからであり、 それはそのとおりだと思う。 しかし、その関係性というものは経脈(けいみゃく)のありかたによって、 たとえば陰の経脈と陽の経脈のありかたによって、 あるいは陰の経脈と陰の経脈のありかたによって、 蔵府(ぞうふ)の病證(びょうしょう)が出るというような関係だと思う。 蔵府(ぞうふ)の病證(びょうしょう)と経脈(けいみゃく)の病證(びょうしょう)を結び付けるとするならば、それしかないと思う。
○10 五蔵(ごぞう)と七竅(しちきょう)や皮・脈・肉・筋・骨との連関は、 どういう連関か。
*七竅(しちきょう)は経脈のあらわれではなくて、五蔵(ごぞう)のあらわれである。 古典的には五蔵の目・耳・口・鼻あるいは、からだの皮毛であるとか、表皮からの深さである皮・脈・肉・筋・骨は五蔵の支配領域である。
**「七竅(しちきょう)」について
『素問』「金匱真言論篇(きんきしんげんろんへん)第四」から抜粋しています。(松本)
肝(かん): 開竅於目 【 竅(きょう)を目に開く 】 , 心(しん): 開竅於耳【 竅(きょう)を耳に開く 】 ,脾(ひ): 開竅於口 【 竅(きょう)を口に開く 】 , 肺(はい): 開竅於鼻【 竅(きょう)を鼻に開く 】 , 腎(じん): 開竅於二隂 【 竅(きょう)を二陰(にいん)に開く 】
○11 五蔵(ごぞう)の〈作用〉とは何か。 それはどのように臨床的に使うことができるか。 腎者。 作強之官。 技巧出焉。 (靈蘭秘典論篇 第八) 腎者。 主蟄封藏之本。 精之處也。 其華在髪。 其充在骨。 (六節藏象論 第九)
*現在の中医学の場合は、 現代の医学のように五蔵(ごぞう)の作用というものを設定し、 現代医学のように病気を説明するということがある。 おそらく現在、中医学で大きく求められているものは、現代の医学による影響があるように思う。 五蔵六府(ごぞうろっぷ)を現代医学のように考えて使うから、 五蔵の作用という発想が出来るのだと思う。
*あくまでも症状や脈状からでしか、経脈(けいみゃく)も五蔵(ごぞう)も、遡及(そきゅう)できないものだと、わたしは思う。
*「腎(じん)は作強(さきょう)の官(かん)」というのが何かであるが、 ここでは腎(じん)という実体の存否が問われる。 腎(じん)は作強(さきょう)の官(かん)という表出の中に、ある種の落とし穴があるように思う。『素問』の 「靈蘭秘典論篇(れいらんひてんろんへん) 第八」や「六節藏象論(ろくせつぞうしょうろん) 第九」は新しい時代に書かれたものと言われている。 二つの篇が、こういうかたちをしているのは、とても象徴的である。 これらの篇が書かれる以前にまで遡(さかのぼ)って考えていかないといけないか、そんなふうに思う。
○12 背部兪穴(はいぶゆけつ)や腹部募穴でなぜ蔵(ぞう)の診察ができないのか。 *これは出来る可能性があると思う。
*背部の兪穴(ゆけつ)を触って、どのような状態であれば、たとえば肺兪(はいゆ)という穴(けつ)を触って、こんな状態であれば肺(はい)の実(じつ)であるとか、 肝兪(かんゆ)という穴(けつ)を触って、このような状態であるから肝(かん)の実(じつ)だとか、肝(かん)の虚(きょ)だとか、そんなふうに診断することは出来るかもしれない。 ここでは経脈(けいみゃく)は関係しない。 蔵(ぞう)の診察はやろうと思えば出来得るかもしれない。
*『難経(なんぎょう)』という本では、蔵府論的に募穴(ぼけつ)や兪穴(ゆけつ)を位置づけている。 だから出来ないことはないように思われる。
*『霊枢』の森を歩いてみませんか。 毎月休まず第二日曜午前10時から12時まで、大阪府鍼灸師会館3階です。 勉強会の案内につきましては本会ホームページをご確認下さい。
次回は 10月12日(日)、『霊枢』「病傳(びょうでん)) 第四十二」 です。
(霊枢のテキスト〈日本内経医学会 発行,明刊無名氏本〉 は現在1冊の在庫があります。1冊1,600円です。受講申し込み時、または当日、受講受付けにてお問い合わせください)
(霊枢勉強会世話人 東大阪地域 松本政己)